その体の不調「寒暖差」が原因かも・「5つ」の症状と予防法まとめ

なんか最近、体調が優れないと思っている方、もしかしたら「寒暖差」が原因かも!医師に5つの症状とその予防法を教えていただきました。ちょっとしたことで症状が楽になるかも。
「寒暖差」で起こる5つの体への影響
【1】冬季うつ
「冬だけでなく、環境の変化や新しい人間関係に適応が認められるような時期には季節を問わず自律神経は乱れます。
冬は寒暖差が大きく、期末の多忙さなどによる仕事のストレス、学生であれば受験など、心理的ストレスによって自律神経が乱れやすい時期です。特に冬季にうつになる状態(まれに夏にうつになることも含む)を季節性うつ病(seasnal affective disorder:SAD)といいます。
冬になると決まって眠くて、だるくてたまらない、理由もなくなぜか気分が落ち込み、寝ても寝ても寝足りない。そして炭水化物を食べたくてしかたない。ところが春になるとウソのように元気になる。そんな症状がある人は“冬季うつ”かもしれません。
一般的なうつ病と季節性うつ病(冬季うつ病)は症状が異なります。落ち込みという状態は共通していますが、うつ病は身体症状としての不眠、食欲低下が特徴です」(牧野先生)
【2】疲れやすいイライラする

「VISION PARTNER メンタルクリニック四谷」院長
尾林誉史先生
おばやし たかふみ/東京大学理学部卒業後、「リクルート」に入社。その後、弘前大学医学部学士編入、東京都立松沢病院を経て、東京大学医学部附属病院精神神経科に所属。今年5月にカウンセリングをもっと気軽に受けてほしいとクリニックを開業。

気温の寒暖差や気圧の変動によって自律神経のバランスがくずれ、気分障害を発症する。自律神経にストレス反応が起こると交感神経が優位な状態のままになって、抑ウツやめまいなどを引き起こしてしまう。
【3】夏の冷え

御苑アンジェリカクリニック院長
神藤慧玲(しんとう えり)先生
千葉大学医学部を卒後後、千葉県内・東京都内の大学病院をはじめ北里研究所病院東洋医学研修や慶愛クリニックにて臨床経験を積み、2017年新宿御苑前に「御苑アンジェリカクリニック」を開院。西洋医学と東洋医学の知見を生かして婦人科系、冷え、妊活外来、鍼灸治療など、あらゆる角度から最適な治療を提案。
「人間の体温は血管の収縮と弛緩を繰り返し、自律神経が正常に働くことで調節されています。ところが寒暖差が激しかったり冷たい飲食物を口にするなど体温の変化が極端になりがちな夏場は、体温調節中枢で本来の体温をはっきりと感知できなくなります。これに連動するように自律神経の働きが乱れ、体温調節が上手くいかなくなるのです」(新藤先生)
【4】めまい

せたがや内科・神経内科 クリニック院長
久手堅 司先生
くでけんつかさ/医学博士。東邦大学附属医療センター大森病院などを経て’13年にクリニックを開業。都内でも珍しい「気象病・天気病外来」は、雑誌をはじめメディアで話題に。
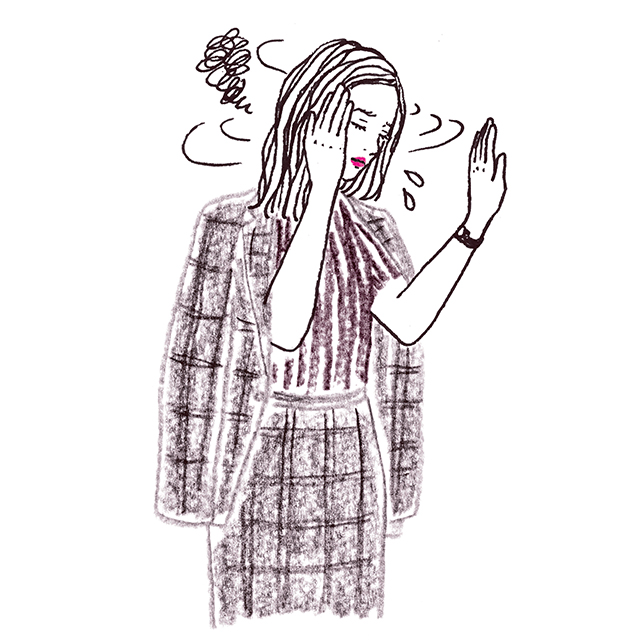
「寒暖差が激しくなる季節の変わり目は、天井がぐるぐると回り立っていられない程に」(メーカー ・35歳)
「“気象病”とは、気候や天気の変化が原因で起こる体の不調の総称で、首・肩こりや、めまい、倦怠感、頭痛など、人によりさまざまな症状が出るのが特徴です。特に気圧、気温、湿度など、気象が大きく変化する時期に起こりやすく、自律神経が乱れることが原因とされています。中でも症状が出やすいのは“気圧の低下”。梅雨前線に沿い低気圧が日本列島を横断する梅雨の頃は特に患者が増えます。“気象病”は医学的に認められた病名ではないものの、現代人の9割は自律神経が乱れていると言っても過言ではなく、悩んでいる人が増えたことで、近年では認知度もかなり高くなってきています」(久手堅先生)
【5】寒い所から 暖かい所に入ると、急に体中がかゆくなる

寒暖差アレルギーかも!
「疲れやストレスによる自律神経の乱れで、温度差が7°C以上になるとかゆみを感じる“寒暖差アレルギー”の場合も」(友利先生)
寒暖差での体の不調「5つ」の予防法
【1】季節性うつ(冬季うつ)には日光浴を

心身医療内科専門医
牧野真理子先生
牧野クリニック 心療内科 診療部長。医学博士。心身医療内科専門医。優秀臨床専門医。北里大学医学部、メルボルン大学医学部大学院卒業。働く女性たちのメンタルヘルス事情に通じ、摂食障害やうつ病の治療に取り組む。患者自身が悩みの解決法を見つけられるよう、親身なカウンセリングでサポートしている。
「体を冷やさないことや日光を浴びることが有効です。私は“冬季うつ”の研究もしており、光療法をラット(ネズミ)に施行して脳内のモノアミンの動きを見てみました。すると光を当てるとラットはセロトニンやドーパミンが増えて元気になりました。このことからも、日光を浴びることが大切なのがわかります。
ビタミンB12を積極的に摂るのもおすすめです。ビタミンB12は光の感受性を高めることがわかってきています。食品では、のり、牡蠣、シジミなどの貝類、いくら、サンマなどの魚類、牛、豚、鶏レバーなどに含まれています。卵、牛乳もよいでしょう」(牧野先生)
【2】疲れやすいイライラにはポジティブなコミュニケーションを

「VISION PARTNER メンタルクリニック四谷」院長
尾林誉史先生
おばやし たかふみ/東京大学理学部卒業後、「リクルート」に入社。その後、弘前大学医学部学士編入、東京都立松沢病院を経て、東京大学医学部附属病院精神神経科に所属。今年5月にカウンセリングをもっと気軽に受けてほしいとクリニックを開業。
リモートワーク疲れなど急激な環境の変化が追い討ちをかけ、睡眠障害の引き金になり疲れやイライラ、うつを起こす原因に
「意識的に『ありがとう』『よくできているね』というポジティブなコミュニケーションを増やすことが大事」(尾林先生)
【3】冷えには体の保温を

御苑アンジェリカクリニック院長
神藤慧玲(しんとう えり)先生
千葉大学医学部を卒後後、千葉県内・東京都内の大学病院をはじめ北里研究所病院東洋医学研修や慶愛クリニックにて臨床経験を積み、2017年新宿御苑前に「御苑アンジェリカクリニック」を開院。西洋医学と東洋医学の知見を生かして婦人科系、冷え、妊活外来、鍼灸治療など、あらゆる角度から最適な治療を提案。
「温かい飲み物や体を温める食事などで対策すると良いでしょう。また、日頃から体を冷やさないように過ごしていただきたいですね」(新藤先生)
【4】めまいなどの気象病は「副交感神経」とのバランスをとる

せたがや内科・神経内科 クリニック院長
久手堅 司先生
くでけんつかさ/医学博士。東邦大学附属医療センター大森病院などを経て’13年にクリニックを開業。都内でも珍しい「気象病・天気病外来」は、雑誌をはじめメディアで話題に。
「体を興奮させる“交感神経”とリラックス状態にする“副交感神経”のバランスをとることで、健康を維持します」(久手堅先生)
【5】寒暖差によるかゆみは緩やかな温めを
「体を急激に温めるストーブは避け、エアコンで室内を緩やかに温めるなど、徐々に体を温めると回避できます」(友利先生)
※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。












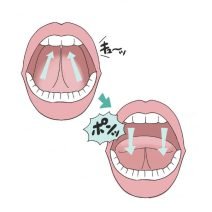


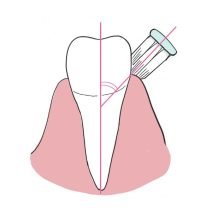


牧野クリニック 心療内科 診療部長。医学博士。心身医療内科専門医。優秀臨床専門医。北里大学医学部、メルボルン大学医学部大学院卒業。働く女性たちのメンタルヘルス事情に通じ、摂食障害やうつ病の治療に取り組む。患者自身が悩みの解決法を見つけられるよう、親身なカウンセリングでサポートしている。