起きたらすぐに朝食を食べたほうがいいってホント?真相を専門家に直撃!【美容の常識ウソ?ホント?】
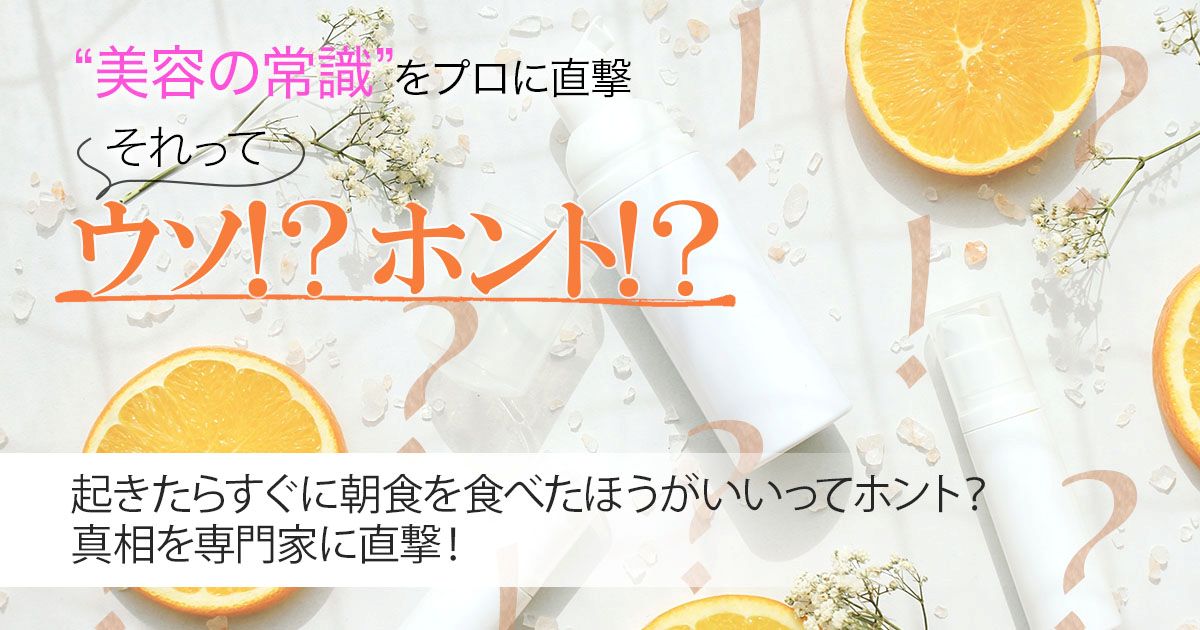
日常生活で生まれる美容や女性のライフスタイルの疑問を医師や専門家に答えてもらうこのコーナー。今回は「朝食」について。朝起きたらすぐに朝食を食べたほうがいいってホント? 理学博士・管理栄養士の古谷彰子さんにお話を伺いました。
Q:朝起きたらすぐ朝食を食べたほうがいいってホント?
みなさんは朝食を食べていますか? そもそも眠たくて睡眠を優先してそのまま出勤してしまい、就業時間中に小腹を満たすという人もいるかもしれませんね。また、「朝は食欲がわかない」からといった理由で、起床後、しばらく過ごし、休日などは10時ごろのブランチが常、という人もいるのではないでしょうか。しかし、「朝食を食べるなら朝起きてすぐのほうが体によい」というウワサが。本当なのでしょうか。この疑問について理学博士・管理栄養士の古谷彰子さんに聞いてみました。
A:ホント
「絶対に起き抜けに食べなければいけない、ということでもありませんが、せめて起床後、1~2時間以内を目安に朝食をとるのがおすすめです」(古谷彰子さん・以下「」内同)
朝食は起きてから1時間以内に食べたほうがいい理由
「朝は活動をはじめる前ですし、特に、夜遅くに食事をしてしまうと起きてすぐにはお腹が空いていない、という人もいますよね。しかし、朝食を食べることで1日をスムーズにスタートさせられることができますし、1日全体を通したメリットも多くあります。
ひとつは朝食には体内時計をリセットするはたらきがあること。ただし、朝食は起床から1時間程度で食べないと体内時計のリセットにはりません。さらに、たとえば10時ごろになって空腹を感じてから食べてしまうと、ついつい食べ過ぎてしまうというデメリットも。朝食と昼食の間は消化の時間を考えると3時間はあけたほうがいいので、12時にお昼という人は、逆算して朝食は遅くとも9時までには済ませるようにしましょう」
体内時計とは?
「体内時計というのは私たちの身体にある1日のリズムを刻む時計を指します。体内時計によって私たちは朝起きて、夜眠くなるというリズムを刻むだけでなく、ホルモンの分泌や栄養の代謝、免疫状態なども調整しています。そして体内時計は24時間よりも少し長いリズムを刻んでいるため、毎日リセットすることが必要です。
体内時計は脳に“親時計”があり、そのほかの脳の各細胞、胃、腸、肝臓、腎臓、そして血管や皮膚など末梢器官には“子時計”が存在します。身体の部位ごとに時計が異なるため、毎日調整しなければ、どんどんズレていってしまいます。そして体内時計をリセットさせるのに必要なのが、朝起きてすぐに朝食をとることなのです」
起きてすぐの朝食は、体内時計をリセットするもっとも簡単な方法です
「朝食を食べれば、親時計の指令がなくても胃や腸などが活動するため子時計をリセットすることができます。運動でも朝食をとるのと同じリセット作用が行われますが、起きてすぐの運動はハードルが高いのではないでしょうか。
また、親時計を介して小時計に指令を伝えるものだと光の刺激があります。目を覚ますために太陽の光を浴びる、といった行為です。しかしこれも、紫外線のダメージが気になる昨今では習慣にしにくいのではないでしょうか。それらを考慮しても、起きてすぐに朝食をとるという行為は、もっとも確実で手っ取り早いといえます。
平日も休日も起床と朝食時間を揃えるのが〇
それから、朝食は、毎日決まった時間に食べたほうが体内時計のリセットにも、腸内環境にもよいです。30分くらいは誤差はOKですが、1~2時間変わってしまうと、生活リズムの乱れによって生理的な体内時計と社会の動きのズレが生じます。規則的に朝食を食べていない人は、時差ボケのような症状が出る“社会的時差ボケ”になりやすいというデータもあるんですよ。平日も休日も、起床と朝食の時間は同じにするのがおすすめです。
そして、ふたつめのメリットは、“セカンドミール効果”を期待できることです」
セカンドミール効果とは?
「セカンドミール効果とは、最初にとる食事(ファーストミール)の血糖値の影響が次にとる食事(セカンドミール)の血糖値にも影響を及ぼすという理論です。たとえば朝食をファーストミールとすると、次の昼食に与える影響のこと。この場合、朝食には血糖値の上昇を抑制するはたらきもあり、朝食を食べなかった人は昼食をとった際に血糖値が急上昇するのに対し、バランスのよい朝食をとった人は食後の血糖値の上昇が緩やかになります」
タンパク質摂取のゴールデンタイムは朝
「そして3つめのメリットとなるのが、朝食でとったタンパク質が最も効率よく筋肉をつくるため。これから活動する時間帯はエネルギー代謝が上がるのです。筋肉の衰えを防ぐにも有効なので、しっかりタンパク質を摂るように心がけましょう。
また、朝にタンパク質は、昼食のみならず、夕食の血糖値も上がりにくさせます。睡眠ホルモンといわれているメラトニンの材料となるトリプトファンがつくられるのもタンパク質から。夜の睡眠の材料となり、睡眠と覚醒のリズムが構築されやすくなりますよ」

愛国学園短期大学 准教授/博士(理学)/管理栄養士 早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構招聘研究員 アスリートフードマイスター認定講師 発酵料理士協会特別講師
古谷彰子(ふるたに・あきこ)
文/土屋美緒
※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。







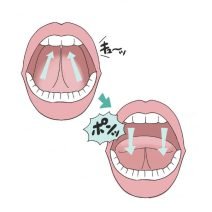


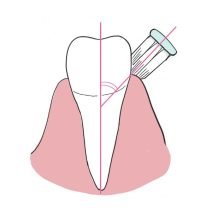




「時間」という観点から、医学・栄養学・調理学の領域にアプローチすることを専門とし、科学的根拠を基にしたライフスタイルへのアドバイス、時間栄養学的栄養指導、実体験を基にした食育活動や講演活動、料理教室も開催中。現場を通じて得た問題点をもとに、ヒトを用いた臨床試験、官能評価、アンケート調査を行うことを得意とする。企業の商品開発や、マーケティングに役立たせることが出来ると好評を博している。メディア出演、連載、著書多数。