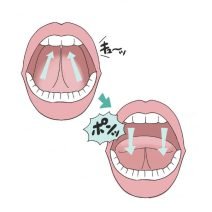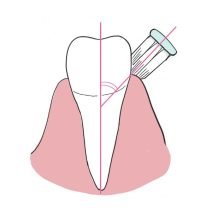咳、くしゃみ、腹痛、下痢…冬の不調の原因かもしれないウイルスや菌の正体を専門家が解説
冬といえばインフルエンザやノロウイルスのピーク時期。しっかり予防することも大切ですが、咳、くしゃみ、腹痛、下痢…etc.冬の不調の原因かもしれないウイルスや菌の正体について細菌学教授の金子幸弘先生が教えてくれました!
ウイルスや菌の正体は?
冬の不調や感染症を防ぐには、まず病原体の性格を知ること!
「高熱や咳、くしゃみ、食中毒などの感染症を引き起こす病原体として、なんとなく同じものと捉えられがちなウイルスと細菌。このふたつ、実は、構造もサイズも性格もまったく違う別ものです。また、まとめて“バイキン”と呼ばれることの多い細菌とカビも、構造が大きく異なるため、対処の仕方は変わります。さらには、同じウイルスや菌、カビの仲間同士であっても、同じ悪さをするとは限らず、増殖する季節や条件もさまざまです」と、細菌学が専門の大阪市立大学大学院教授の金子幸弘先生は話します。冬の感染症や不調を防ぐには、ウイルス・カビ・細菌の、それぞれに合わせた対処法を実践していくことが大切です。
ウイルス
自ら増えることができない生物と無生物の中間的存在
中心にDNAまたはRNAのいずれかの核酸をもち、周りをたんぱく質の殻が包む微小な粒子。0.03~0.3μmで、光学顕微鏡でも見えない。自らの力だけで増えることはできず、基本的にほかの生物の細胞を利用して増殖。
冬に多いのは…
インフルエンザウイルス
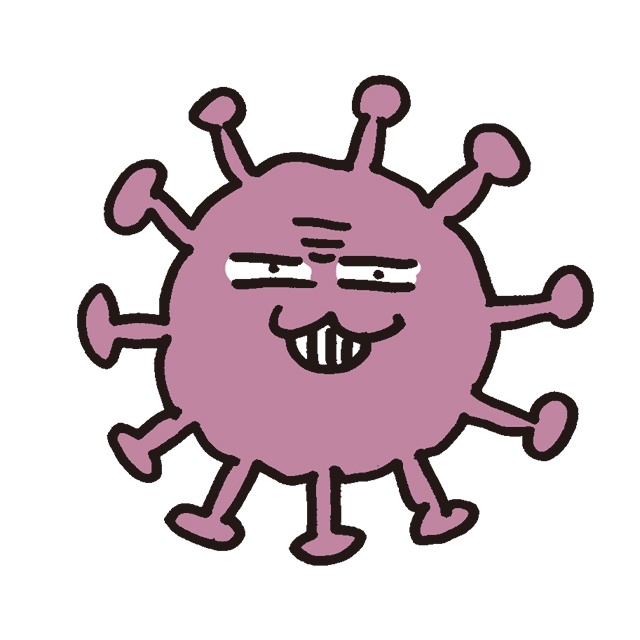
冬の高熱の原因No.1!
インフルエンザウイルスにはA型、B型、C型の3種類があり、感染力が強いのはA型とB型。感染してから1〜3日の潜伏期間を経て発症し、約1週間で改善。ただ長引くと肺炎を起こすことも。
ノロウイルス
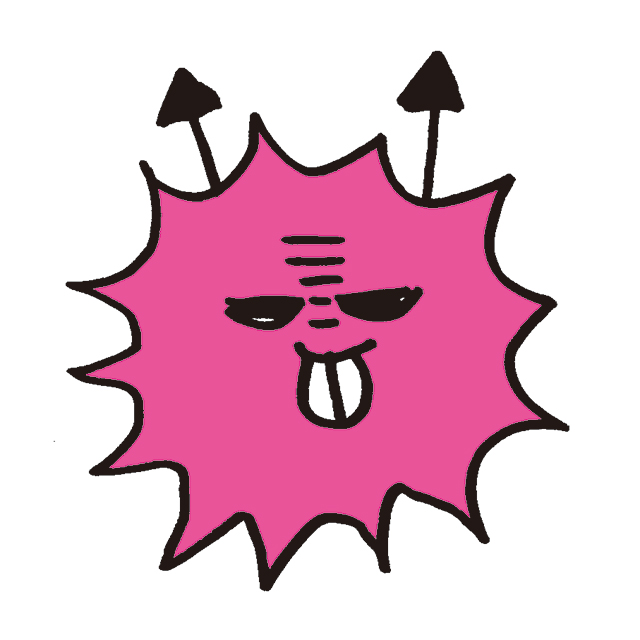
冬の食中毒の原因No.1!
人の腸管内のみで増殖するものの、乾燥に強い上、自然環境下でも長期間生存が可能。感染力が非常に強く、幅広い年齢層に急性胃腸炎などの症状を引き起こします。
カビ(真菌)
酵母やキノコと同じ真菌の仲間で多細胞生物
日常生活で「カビ」と呼ばれるものは専門的には「真菌」の仲間。糸状のものが絡み合った構造のため「糸状菌」とも呼ばれる。約100μm。DNAを格納した核をもつ真核生物で、核をもたない原核生物の細菌とは区別される。
冬にもいるのは…
クロカビ
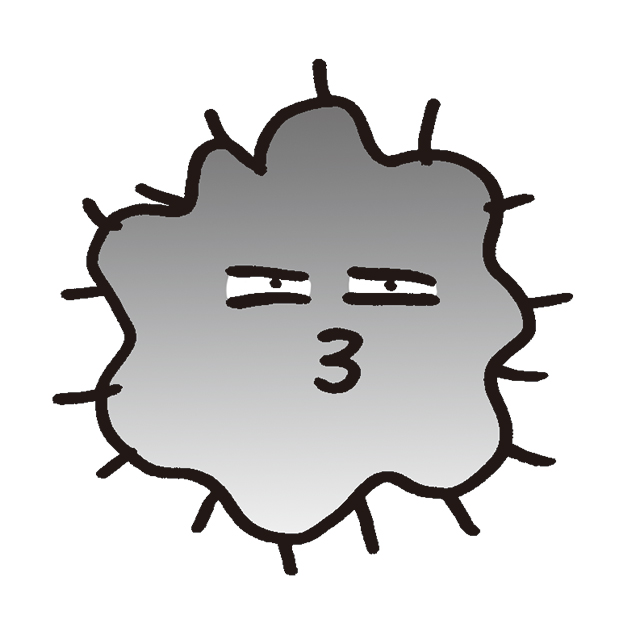
結露の多い所にクロカビあり!
その名のとおり、黒色のカビ。浴室や結露の多い窓付近に生えるカビとして代表的な菌種。低温、乾燥に強いので、マメに退治しないと冬でも増殖。放置するとアレルギーの原因にもなります。
細菌
栄養があれば、自己複製で増殖できる単細胞生物
生きるための最小限の機能を備えた単細胞生物。0.5~4μm。大腸菌やサルモネラ菌、カンピロバクターなど、食中毒の原因になる“悪者”もいれば、乳酸菌など人類の役に立つ細菌も。体内に定着して細胞分裂で自己増殖。
冬にもいるのは…
ウェルシュ菌やボツリヌス菌
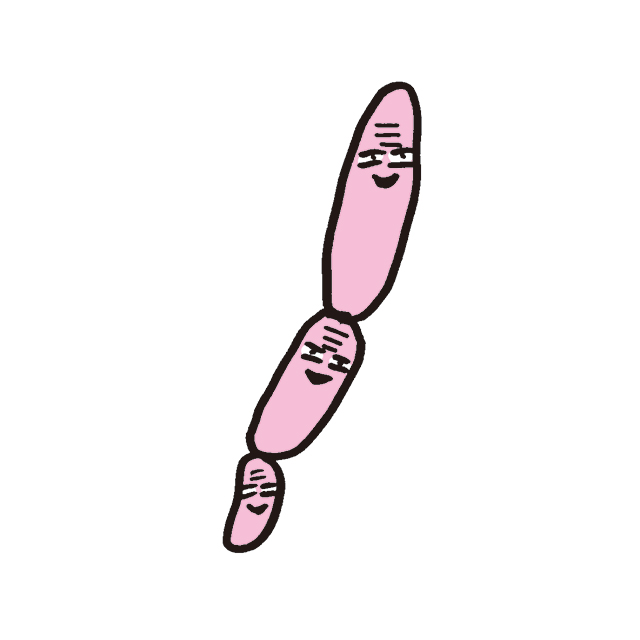
酸素のない所で毒素が増える!
いずれも酸素を嫌う嫌気性細菌。100℃の熱に耐えられ乾燥にも強いため、季節を問わず食中毒の原因に。ウェルシュ菌は煮込み料理、ボツリヌス菌は密封された加工食品に発生しやすい。
ウイルスや菌について教えてくれたのは…
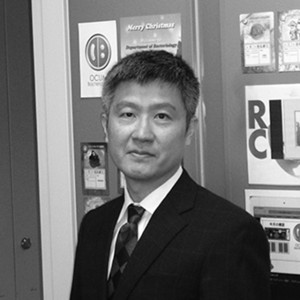
大阪市立大学大学院 医学研究科細菌学教授 金子幸弘先生
かねこゆきひろ/長崎大学医学部卒。医学博士。同大学附属病院に勤務後、研究員として米国ワシントン大学、国立感染症研究所に所属。2014年から現職へ。自ら考案の「バイキンズカード」が話題。
『美的』2020年1月号掲載
イラスト/すぎうらゆう 構成/つつみゆかり、有田智子
※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。